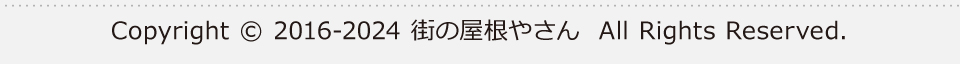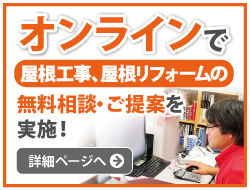

日高市の皆様、こんにちは!
梅雨があけて、いっきに暑い夏になりましたね。
気温を上昇させる直射日光から建物を守る屋根材のひとつの瓦はいつ頃から普及したのでしょうか?
屋根材の瓦は飛鳥時代に仏教とともに伝来したとされています。
寺院やお城に使われて一般の建物に瓦が用いられることはあまりなかったようです。
この時代の瓦屋根は本瓦葺(ほんがわらぶき)といって、平瓦と丸瓦を組み合わせるので、その重さを支えられる建物は、頑丈に造られた寺院や城郭以外には少なかったというわけです。


1657年、振袖火事と呼ばれる大火事が江戸の街を焼き尽くして、江戸城も一部を残して焼け落ちたといいます。
当時の町人の家は密集していて草葺きか板葺きで火事が出れば大規模火災になることが多かったのです。
この後、幕府は、消火の際に瓦が落ちて危険だという理由で、既に瓦屋根が普及していた武家屋敷、大名であっても土蔵以外の建物を瓦葺きを禁じる命令を出しました。
防火を考えると、納得できないこの禁令は約60年続いて、やっと八代将軍吉宗の時に解かれました。火災防止のために瓦葺きの許可を願う「目安箱」の投書が取り入れられたとあります。
そして、これを機に防火対策のために江戸の町屋の瓦屋根化を奨励するようになりました。
瓦屋根に改築するためのお金の貸付などもあり江戸の町は、少しずつ瓦葺きになっていきました。
幕府による奨励策、一般庶民にも利用できる10年ローンの拝借金制度。江戸時代をみなおしてしまいますね。
そして、「桟瓦(さんがわら)」の発明が一般家屋への瓦屋根の普及に大きな力になりました。
桟瓦(さんがわら)は、それまでの本葺き瓦の平瓦と丸瓦を一つにまとめたもので、製造や施工のコストを抑え、軽量化に成功しました。

法の改正と技術の進歩で瓦屋根が一般の建物に普及したわけですね。
現代では、耐震性、断熱性、防水性に優れて、メンテナンスに手がかからない屋根材としての瓦が開発されています。ハイブリット瓦のROOGA(ルーガ)は、さらに2020年、不燃材料認定取得、耐火構造認定を受けています。
古くから愛され使用されてきた瓦屋根。

街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん所沢店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.